内面深掘りで気づきを促し、行動を変える薬剤師
「セルフラブとコーチングで、育児ママを支えて救いたい」
薬剤師兼ワーキングママの願望実現コーチとして活躍する浅岡愛子さん。
大学の薬学部を卒業後は調剤専門薬局に就職し、出産・育児に突入するも自己肯定感のどん底を経験。そこで愛子さんを救ったのは、あることがきっかけで気が付いた自己流セルフラブでした。
愛子さんを動かしていた3つの性質と、コーチングを学んで気付いた3つの愛。
ブレイクスルーの軌跡とモットー、そして薬剤師兼コーチとしての在り方について伺いました。
「私の名前は両親が『人を愛して愛されるように』という意味を込めて名付けてくれました。
私は他に3つの意味があると思っています。
1つ目が自己愛=セルフラブ。
2つ目が慈愛=親身になるということ。
そして3つ目が博愛=ご縁を大切にするという意味です。
この3つを肝に据えて、現在は薬剤師として働きながら、コーチとしても活動しています」
困っている人を支える仕事がしたい

薬剤師になろうと思ったきっかけは、高校生の時に見た医療ドラマだった。
『困っている人を支える仕事がしたい』
そう決意し、大学は薬学部へ進学。卒業後は総合病院の門前薬局で勤務するも、理想と現実のギャップを感じることとなる。
「もっとじっくり患者さんの話を聞きたいと思っていたんですが、実際はとても忙しい職場でした。ほとんど喋ることなく流れるように過ぎてしまうところに大きなギャップを感じていました」
その後、妊娠・出産・育休を経てドラッグストアへ異動。働き方は一転し、色々な質問や相談に乗るようになった。
自己流セルフラブで、あるがままの自分を受け止める

コーチングに辿り着いたのは、育児がきっかけだった。
「以前の私は3つ特徴がありました。ネガティブで、その心配を努力でカバーしていた点、何が何でも正解が知りたい点、そして、他人の評価が自分の価値だと思っていた点。
つまり、あるがままの自分を受けとめられていませんでした。
20代まではそれで回ってたんですが、育児を始めてからは全く通用しなくなって、どん詰まりになっちゃったんです。
育児って努力しても成果が出るものでもないし、正解もない、誰かがほめてくれるわけでもない。
紆余曲折を経て自己流のセルフラブで立ち直ることができたんですが、その時から、自分と同じような人を支える仕事がしたいと思うようになりました」
ネガティブ→ポジティブ変換で自分を取り戻す
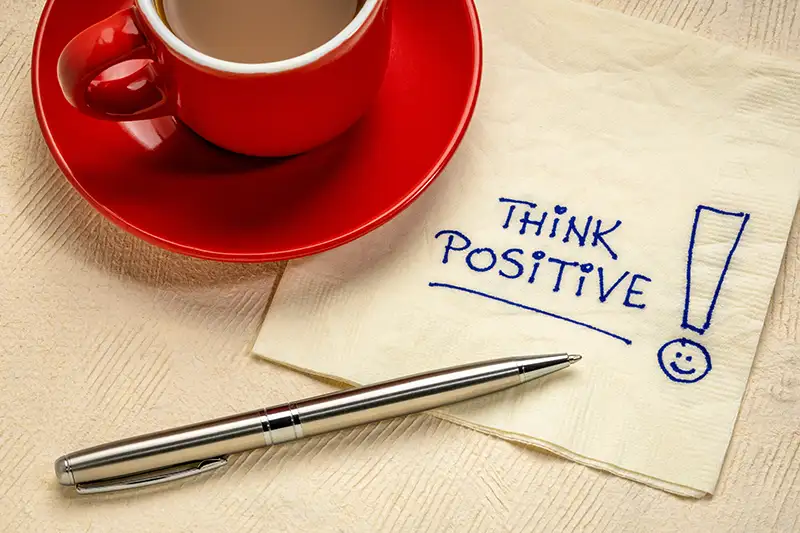
育児中は、毎日自分を責めていたという。
「私は育児が苦手で、家事も好きじゃありませんでした。でも家にいるので、育児と家事はしなくてはいけない。
でも、やりたくない。そんなできない自分を見るのが嫌で、自分のことをダメな母親だと責めていました」
自己愛に気付くきっかけとなったのは、旦那さんの存在だった。
「夫はしっかり者なんですが、家だと気が抜けるタイプで、家事もしない。でも夫は夫自身のことが大好きだと思っていると、気付いたんです。
そうしたら、『この人よりましかも』って思っちゃった。
つまり私は、自分のことが好きになりたかったんですよね。
それに、子供が自分自身を毎日責めるようになったら嫌だとも思いました。その時から、自分のことが嫌いだとか、この生活から逃れたいと思っていた後ろ向きなところから、前を向こうと思うようになりました」
まずはネガティブをポジティブに変換することから始めた。
「例えばお茶をこぼした時、前なら気持ちが沈んでいたんですが、『お茶をこぼしたということは、この机をピカピカに磨くチャンス!』と思うようにしました。
すると不思議と自分を取り戻した感覚がしたんです。そういうことを繰り返していくと、だんだん『私ってダメじゃない』、『私っていいかも』と感じられるように変わっていきました」
自分と同じような思いの人を支える仕事がしたい

最初は、思いを形にする方法が分からなかった。
「パートとして働きながら活動するのは、社内制度として難しかったので半ば諦めかけていましたが、それから数年後、起業という方法に気が付きました。
それで、起業して、人を支えて救っていく方法を探していた時、ゆりさんのコーチングスクールに出会いました」
自主性を重んじるという点で、提供したいサービスとコーチングが重なった。
「私は育児で自主性を重んじることでその大きな効果を感じていて、事業でもそのようなサービスを提供したいと考えていました。
一方的にアドバイスするのではなく、お客様の中にある答えを引き出すことが重要だと思っているからです。
その点がコーチングと一緒で、ぴったり!と思ってコーチングを学ぶことに決めました」
“他人の目が気になる”を根っこから引き抜いた

「コーチングを学ぶまでは、自分で解決できない悩みに対しては、とりあえずの対処法で済ませることばかりでした。
例えば“人のせいにする”、“力不足だからしょうがないと諦める”、“我慢する”、ですね。
コーチングを学んでからは、自分の本心や潜在意識に向き合うことで、他の対処法があることが分かったんです。
しかもその方法なら、同じことを繰り返さないし、根っこでつながっている他の課題も解決できると分かりました。
例えば、私にはずっと許すことができなかった人がいたんですが、コーチングを学ぶことで許すことができたんです。正確には、“許す”というプロセスもなくて。
本心を深掘りして行ったら、根本には“他人の目が気になる”という気持ちがあったので、それを手放しました。
そしたらその人を許すことができていたんです。
他にも、SNSに対する危険だという思いがリリースされて、実名顔出しができるようになっていました」
薬剤師としては、「私には“安心・安全にお薬を渡す”というモットーがあるんですが、お客様がたくさん待っていらっしゃる時はいつも焦っていて、目の前のお客様に集中できていませんでした。
実はその状態も“他人の目が気になる”という思いから生じている反応のひとつだったんです。
“他人の目が気になる”を根っこから引き抜いて手放したら、次に出勤した時、普段通り仕事をしているのに気持ちが全然違ったんです。すごくリラックスして、モットーに沿って対応できていました」
コーチングを学ぶことで周囲との関わり方にも変化があった。
「“メタモデル”も非常に役に立っています。
『全部って具体的に何ですか?誰がダメって言ってるんですか?』と、突っ込んだ質問をすることで、言葉の裏に省略されていることにお客様自身が気付かれて、解決に至るようになりました。
娘とのやり取りにもいい変化がありました。
娘が急に泣き出した時、『本当にそうなの? これってこうだからこう?』と、少しずつ話を紐解いていくと、最終的には『大丈夫』という結論に行きつきました。
以前だと慌てていたんですが、そういう関わり方ができるようになりました」
薬局での自己開示とコーチング

コーチングでクライアントからの自己開示が大切なように、薬局でも患者さんからの自己開示が非常に重要となる。
「処方箋の調剤においては、患者さんの情報は処方箋1枚です。
アンケートやお薬手帳から副作用や服用中の薬についての情報をいただいて、処方箋と紐付けることで問題がないか確認しています。
なので患者さんから自己開示いただけない場合、処方箋1枚の情報だけで薬を出すのは、実は心許ないんです。自己開示によって正確な判断ができるという側面があります。
当然医師も患者さんから聞き出してくれているんですが、人間なのでカバーしきれないところもあります。
なので、患者さんの自己開示と医療関係者の質問力って、治療にすごく関係しているんです」
実はアメリカでは、薬剤師が糖尿病の治療に介入しています

薬剤師としての治療への関わり方について、愛子さんには一歩踏み込んだ考えがある。
「糖尿病って、日本だと9割以上が2型糖尿病と言われています。2型は生活習慣病なので、生活習慣を変えることで数値が改善します。
でも、『頭では分かっていてもできない、続けられない』ために、なかなか生活習慣を変えられない人が多いのが現状です。
なので『~した方がいい、~してはだめ』と伝えたところで効果は出ないと思っています。
実はアメリカでは、糖尿病の治療に薬剤師が介入しています。
“アッシュビルプロジェクト”という有名なプロジェクトでは、薬剤師が積極的な服薬指導や生活指導などの薬物治療管理を患者さんに定期的に行いました。
具体的には患者さんの糖尿病療養に関する知識の確認、定期的に検査を受けているか、正しく薬が使えているかの確認をします。
足りないところを薬剤師が補足することによって、5年間で医療費を34%削減する成果が上げられました。
今、こういったプロジェクトを参考に、自己理解を深めながら主体的に生活習慣を改善していくコーチング要素を強化したプログラムを作っており、店内のスタッフを対象に試験的に導入しています。
こうしたプログラムの提供を通して、糖尿病を予防できるようになりたいですね。
ハードルは低く、価値は正しく

今後は、コーチングを日本でもさらに広めていきたい。
「私の周りではまだまだコーチングを知らない人が多いですし、深い悩みを持つ人が受けるものだと思われていたり、値段だけを見て敬遠されている側面もあります。
例えば飛行機のチケットや食洗機って、それによって得られる価値を理解したら高くても買うと思うんですよね。
コーチングは自分のゴールや目標にたどり着くための時間とエネルギーを短縮してくれるものです。コーチングによって得られるものの価値を知って欲しいですね。
深い悩みがある時、自己開示をすることにハードルを感じる方もいらっしゃると思います。
そういった方向けに、気軽に未来逆算のコーチングを体験できるプランをご用意しています。
いずれは、かつての私のように、自分を受け止められなくて苦しんでいる方をサポートできるようなプログラムを作りたいと思っています」


