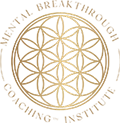カウンセラー×コーチング。幅広いサポートを通して生きやすい世界を作りたい
「社会の期待ではなく、自分のパッションに沿って生きる」
臨床心理士・公認心理師・コーチとして活躍する小坂宏子さん(通称あきさん)。
大学の学生相談室に臨床心理士として勤務するかたわら、起業して『心理オフィスあき』を主宰。
ニューロダイバーシティやポリヴェーガル理論など様々な学びを融合した視点から、コーチングの役割やカウンセリングとの共通点、発達性トラウマ、そして目指す世界について伺いました。
マイナスの方へのカウンセリング、マイナス寄りからのコーチング
「精神科病院では、生きていくのが大変な方たちのサポートをしてきました。
その後、働く人や大学生のサポートを始めたわけですが、それまでのアプローチではしっくりこないということがありました。
今まで学んできた臨床心理学は“マイナスの人”を対象としていたため、生きることに難しさを感じているけど会社にも学校にも来られている人達が、より前向きに人生を進めていくためのサポートをしようとすると、手法が分からなかったんです。
当時、同じ1対1のアプローチとしてコーチングの存在は知っていましたし、コーチングでは“ゼロをプラスにする”と伺っていたので、マイナスをあつかうカウンセリングとの違いを知りたいと思いました」
最初に学んだのはポジティブ心理学コーチング。
そこでは明確に、マイナス寄りにいる人は対象ではなかった。健康度が高い人へのアプローチとしては有効だと感じる一方、“本当にプラスの人”がいるのか疑問を持つようになった。
「カウンセリングや精神科、心療内科にいらっしゃらないからゼロとかプラスなのかというと、決してそうではないように思えて。そうすると、コーチングをしてもすっきりしない方や、モヤモヤが残ってしまう方たちがいらっしゃることに気付きました。
その後、ゆりさんのスクールを受講しました。
そこではマイナス寄りのモヤモヤやトラウマを抱える人に対してもコーチングをされていました。
“マイナス寄りからのコーチング”ということが、むしろそっちの方が人間らしいんじゃないかと、すごくしっくりきたのを覚えています」
ほんの些細な出来事が自分の足を止めていた

コーチングスクールを受講し、学んでいく中で意外な気付きがあった。
「自分自身がコーチングを受けることで、自分では導けない視点に立てました。
また、ほんの些細な出来事が実は自分の足を止めていたことに気付かせてもらって。そういった制限をリリースすることが、私自身の人生を非常に変えることにもなりました」
自分でも気付かないことがトラウマ的な体験となり、その後の価値観やアイデンティティに影響する。そのことにコーチングを通して気が付くこともある。
「日本は特に『我慢が美徳』、『そのぐらいのことで』という文化があります。
例えば女性が痴漢にあうと自分を責めてしまいやすい。自分を責めて、1人で我慢するパターンもあれば、男性に対して闘争心を燃やして生きていくパターンになることも。
本来、自分は何も悪くないんだけど、その時の体験がその後の人生に大きく影響してしまう。親子関係の中でも、親が良かれと思ってやったことが、本人にとってはトラウマ的体験になっていることもある。
そうした体験のなかで大人になって、外からは分からないけれども本人の中では生き辛さがある、という方が多いんじゃないでしょうか。
すごく無理して頑張っていたり、常になにかに怯えていたり、些細なことでパニックになっているけれど、それを努力して見せないようにしてきた。
非常に大きなトラウマ体験に蓋をしているわけではないけれども、生き生きした感情を否定され、良くないこととして育ってきて、グッと我慢している。いうなれば、自分の感情に蓋をして、感じないようにして乗り越えてきた。
でもすごく無理してるので、どこかで力尽きてしまうんですよね。
例えば受験の後、結婚や出産後、仕事で成功した後など。自然体で成功している人はそのままトントンと進めばいいんですけど、全然自分らしくないやり方で努力してきていると、息切れしてバーンアウトしてしまう。
女性でキャリアを積んだ方は、自分の意志でそこまで来たのか、周りの期待に応えるためだったのか、分からなくなってしまうパターンも多いかもしれません」
受け皿としてのコーチング
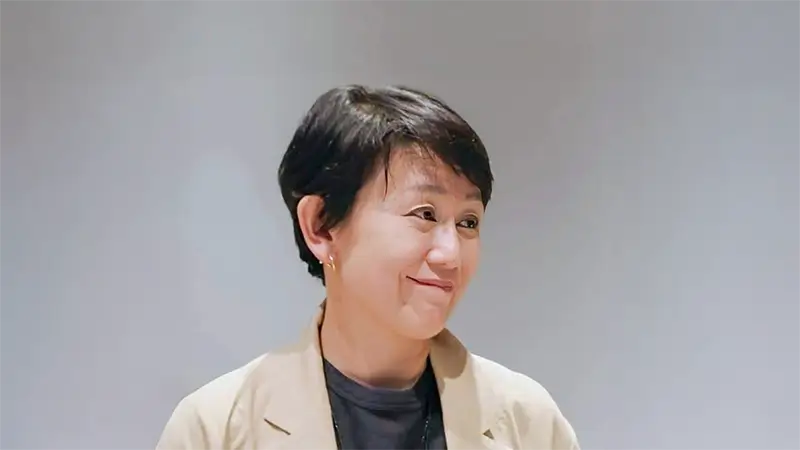
実は、精神的にギリギリの方がコーチングを受けに来られることもある。
「アメリカでボディワーカーをされている方からインタビューを受けた時、『日本ではメンタルのサポートを受けることがすごく特殊な事のように思われているのか?』という質問を受けました。
アメリカではホームセラピストがいるけど、日本には全然そういう存在がないんですね、と。
日本では、弱い自分を見つめて認めることが、『恥』という感覚があるのかなと思っています。
その点、コーチングは自分を成長させる意味付けで受けられるので、入りやすいんじゃないかと思います」
あきさんは現在、カウンセラー兼コーチとして、様々な学生をサポートしている。
「私のいる学生相談室へ来る学生は、具合の悪いマイナス寄りの子から、前向きに成長を目指す子まで様々です。そうするとカウンセリングから始まって、途中からコーチングに切り替わって、卒業まで支援して、いってらっしゃいとなる。
そうやってサポートできるようになったのは本当にやりやすくなりました。
相談室に来ない学生たちにも、セルフコーチング的なケアの方法を知ってもらいたいですね。
私の勤務先は藝術を専攻する大学なのですが、例えばうちの学生であれば、もっといい演奏をしたい時、作品制作で行き詰って誰かにエンパワーメントして欲しい時には、人に相談してもいいんだと気付いてもらいたい。そうすれば卒業後もコーチングやカウンセリングに自分でアクセスできますから。
そうやって外に助けを求めていいんだということも、知って欲しいなと思っています。
起業では、日本では臨床心理士としてカウンセリングからコーチングまでのサービスを提供している人は少ないと思うので、幅広くお役に立てるかなと思います」
自律神経に着目したアプローチ

「脳とか自律神経系に着目したアプローチに関心を持っていて、私の柱の一つである『ニューロダイバーシティ』では、“発達障害も脳の特性の1つ”として捉えます。
私たちはみんな異なる脳の特性を持っているという考え方に基づいたサポートですね。発達特性を持っていて、うつ病などで困っていればカウンセリングが有効ですし、特性を上手く生かしていくならコーチングも適していると思います。
最近、ポリヴェーガル理論や自律神経系の研究から、“発達性トラウマ”の存在が分かってきました。
育つ過程で色々生き辛い体験をしたことが、自律神経系に刻み込まれたトラウマ記憶となって、今の生きづらさを生んでいるというものです。
私たちは『自分は怖がりで、ダメで、しょうもない人間だ』と、あたかも自分の人格であるかのように勘違いしているのですが、それは育ってくる過程で自分の神経系に刻み込まれたことなんです。
これまで心の問題は脳の問題として扱われ、薬で治療されてきました。
けれど神経伝達物質も未解明な部分が多く、特にトラウマ体験には薬が効かないことも出てくる。
そうした中で、ポリヴェーガル理論やソマティックなアプローチに着目したセラピーが有効だという研究が進んでいます。さらにボディワークや鍼灸など、身体的アプローチとコラボレーションした治療法も増えてきています。
こういった背景への理解が進んで、病院に通わなくても自分で自分と向かい合ってある程度乗り越えていけると分かってきたことは、すごくハッピーなことなんじゃないかと思いますし、その先のアプローチとして、コーチング的な関わりをプラスして日常生活をもう少し前向きなものにしていくサポートの場が広がって行くといいですね」
耐性の窓を広げてあげる

自律神経を整えることは、人生の豊かさにもつながってゆく。
「“耐性の窓”という言葉があって、これは私たちが心地よく過ごせる自律神経の動きができる範囲のことです。トラウマ的な経験をしている方は、この範囲がすごく狭くなっていて、安定性が失われているわけです。
なので、大変なことがあると“fight-or-flight(闘争か逃走)”状態になって怒りを抑えられなくなったり、パニックになってしまう。そして“Freeze”(凍結)の状態に入って、動けなくなる。
神経系の上と下にしか行けなくて、真ん中で程よく心地よく、安定した状態になれないのが、感情を抑制して、サバイブしてきた方たちが言う“生きにくさ”でしょうか。この“耐性の窓”を広げてあげることが、カウンセリングやコーチングでできることですね。」
耐性の窓は、人間関係における安心感とも関係している。
「安心感って、やはり人との交流の中にあるんです。私たちは社会的な動物であるので、どうしても人とのつながりなくして安心感は得られない。しかし耐性の窓が狭い状態、すなわち人に対して恐怖や裏切り、攻撃といったフィルターがある状態だと、安心感が得にくくなってしまう。
それは知らないうちにフィルターを通して世界を見ているからなんです。そこではまず自分にフィルターがあることに気付くことから始まります」
「ほんの些細な、笑い話にしてることのなかにも、根底には当時傷付いてたな、って想いがある。そういうことって結構皆さんの中にあるんですよね。そういった小さな出来事もしっかり受け止めて、『だから今、これをすることにストップがかかってるのかな?』とつなげていく。
自分でもできるけど、カウンセラーやコーチ等の第三者と一緒だと解消していきやすい。そうした小さな一歩が、実は私たちの人生にすごく大きな影響を与えます」
自分の過去も、小さなトラウマも、なかったことにしないで丁寧に扱っていく

カウンセリングからコーチングまでを学ぶことで、サポートする幅が広がったと感じています。
大学のなかでもこれまでのサポートは続けていきますが、起業では、もう少し敷居の低いカウンセリングルームにしていきたいと思っています。
皆さんの中では“カウンセラー”ってちょっと敷居が高い感じがあるかもしれません。ですが、『なんでうまくいかない感じがあるんだろう』と思っている方や、プラス方向に向かうコーチングを受けた時に、『何か違和感やモヤモヤが残っている』と感じる方に、ぜひ来ていただきたいです。
もう一つ、ずっと続けているニューロダイバーシティからみた発達障害については、その人が悪いのではなく、それが持って生まれた脳の個性であるということ、色んな生き方があるということを伝えていきたいです。
自分の過去も、小さなトラウマも、なかったことにしないで丁寧に扱うサポートを続けることで、皆さんが生きやすい世界が作っていけたらいいなと思っています。
小坂宏子(通称 あき)
- 臨床心理士、公認心理師、コーチ
心理学科を卒業後8年間会社員として勤務した後、大学院に戻り、臨床心理士資格を取得。精神科病院に長く勤務する傍ら、行政で働く人のカウンセリングルーム、藝術大学の学生相談室立ち上げに関わる。 - 心理オフィスあき主宰
【誰もが自分らしく自分のパッションで生きる】
https://www.psyoffice-aki.com/home
───────────────────────
ニューロダイバーシティからみる発達障害]講座
https://www.psyoffice-aki.com/basic
「自分らしく生きられていないと悩む人たちが、本来の自分らしさを取り戻し、望む未来を生きる支援」を目指し、ニューロダイバーシティやソマティックアプローチをベースに、カウンセリング、コーチング、心理学講座、セルフコーチンググループなど、各種オンラインプログラムを提供している。